昨今、日本各地で台風、地震、豪雨などの自然災害が頻発しており、予測が困難な状況に直面しています。
そんな中、高齢化社会の進展により介護施設の需要が急速に拡大し、その数は年々増加しています。
介護施設は、利用者の安全・安心を確保するため、通常の運営だけでなく、災害時における迅速かつ的確な対応が求められています。
こうした背景から、施設内での防災対策、特に備蓄品の整備や管理の徹底は、命を守る上で極めて重要な取り組みとなっています。
介護事業者におけるBCP義務化
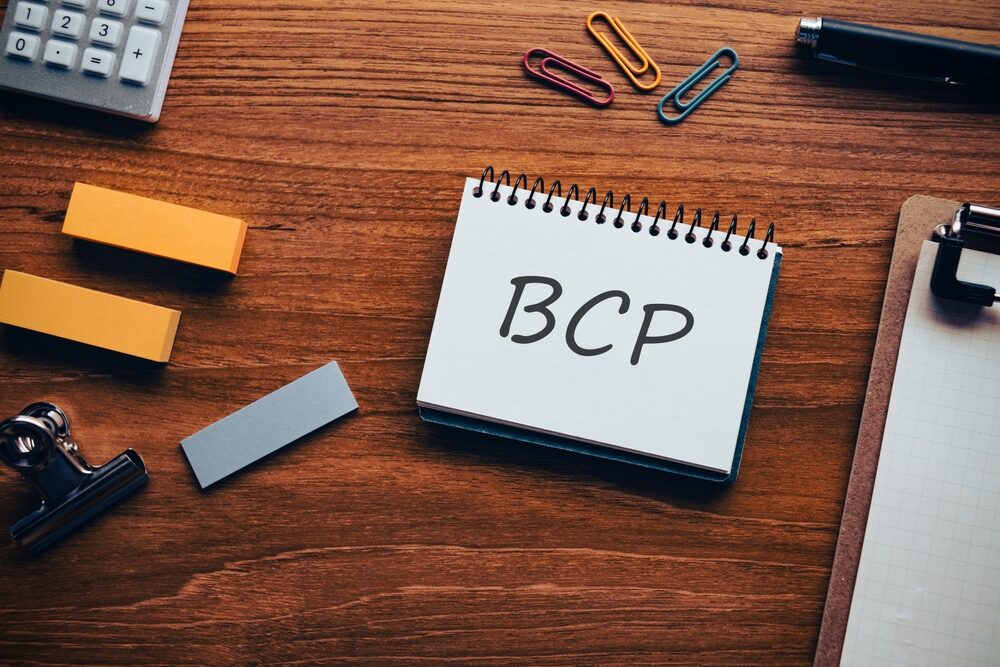
2024年4月に、介護事業者に対してBCP策定の義務化がスタートしました。
この措置は、災害や感染症の発生時においても、介護サービスを継続的に提供することを目的にとられた対策になります。
介護事業者は、新型コロナウイルス蔓延や自然災害などの緊急事態の中でも、安定した介護サービスを提供できる体制を整備し、利用者や職員の安全を確保することが求められます。また、職員の健康・福祉を守るための対策も重要なポイントとなります。
本コラムでは、介護事業者の防災対策において必要な備品・準備を具体的にまとめてまいります。
介護事業者がそろえるべき備蓄品

1.基本の防災備蓄品
以下のような基本の防災備蓄品を、利用者はもちろんのこと職員も含めた人数分を最低限準備しておきましょう。
① 食料/非常食
非常食(カロリー補給食、レトルト食品、保存が効く食事)
目安: 利用者および職員1人あたり3食×7日分(7日間の非常時対応を想定)
※施設全体の人数に応じて、バランスの取れた栄養を考慮し、保存期間の長いものを選定します
介護施設利用者の状況によっては固いパンなどが不向きな場合もあります。
バリエーションを増やすと管理コストへの影響も考えらえますが、施設の状況によって必要な備品のカスタマイズは必要と考えられます。
②飲料水
目安: 1人あたり1日3リットル×7日分
※高齢者の場合、体調に合わせた水分量の確保も必要。
温水・冷水の確保や湯沸かし設備の点検も並行して行います
③衛生用品・消耗品
食料、飲料水に加え衛生用品・消耗品も必要です。
トイレットペーパー、ウェットティッシュ、紙おむつ、使い捨て手袋、マスク、消毒液
目安: 利用者の通常使用量の1.5~2倍分を備蓄し、災害時の混乱を見越した余裕を確保。
簡易トイレ用品・清掃用具
簡易トイレキット、ポータブル便器、消臭剤など
目安: 施設内でのトイレ機能が利用できない場合を想定して、最低1セット以上を非常時用に準備。
④災害対応用品
情報収集・連絡手段
携帯ラジオ、懐中電灯、予備の電池、携帯充電器(ソーラーチャージャーなど)
目安: 各棟または各フロアごとに1セット、職員用として追加で1~2セット
防寒・保温用品
毛布、簡易寝袋、着替え、保温シート
目安: 利用者1人あたり1~2枚分の毛布または寝袋、追加で共用で使用できるものを1~2セット
医療器具
状況によっては医療器具の準備も必要になります。持ち出し可能な備蓄品として準備・まとめることで災害時に清潔な器具を確保でき二次災害の防止につながると考えます。
医療器具としての備蓄品の一例を記載いたします。
① 常備薬・医薬品
利用者個別の常用薬
目安: 各利用者の医療計画に基づき、通常の服用量を最低7日分以上(場合により14日分以上の備蓄が望ましい)
救急用医薬品
解熱剤、鎮痛剤、抗生物質、点滴用輸液、アレルギー対応薬など
目安: 施設全体の急変時に対応できる量として、一般的な緊急処置用として7日分を確保。施設規模に応じて医療機関との連携で補充計画を策定。
② 救急医療器具・応急セット
救急セット
包帯、ガーゼ、絆創膏、止血帯、消毒液、ハサミ、ピンセットなどの基本応急処置用
目安: 施設内の各エリア(各棟や各フロア)に1セット以上、施設全体で最低3セット以上(人数や利用状況に応じた追加備蓄が必要)
③AED(自動体外式除細動器)
目安: 施設内の主要な場所に1台、規模により追加の設置を検討
吸引器および酸素供給装置
吸引器、携帯酸素ボンベ、酸素マスク、ネブライザー(加湿器)など
目安: 利用者の呼吸器系疾患や緊急時対応を考慮し、少なくとも施設に1台は常備。酸素ボンベは、利用者数に応じた数(例:利用者が多い施設では2~3本以上のバックアップ体制)を確保。
その他医療機器
④血圧計、パルスオキシメーター、体温計などの基本計測器
血圧計、パルスオキシメーター、体温計などの基本計測器
目安: 利用者の状態把握のため、各棟または共用で1セットずつ。簡易検温キットは各部屋にも設置可能。
注意点
定期点検・ローテーション管理: 備蓄品および医療器具は、使用期限や性能の低下を防ぐため、定期的に点検し、消費期限切れや故障がないか確認します。
利用者ごとのニーズの把握: 各利用者の健康状態やアレルギー、特定の医療ニーズに応じた備蓄計画が必要です。
地域連携: 地域の医療機関、行政と連携し、非常時の追加支援体制を整備することも重要です。
このように、介護施設における備蓄品と医療器具の選定・必要量は、施設の運営規模や利用者の特性を踏まえたうえで、最低限の非常時対応を確保することを目的として計画されるべきです。最新のガイドラインや地域の実情に合わせた見直しが定期的に行われることが望まれます。
③避難補助器具
自力で避難が困難な施設利用者がいる場合、おんぶひもやマットレスといった補助器具の準備も必要となります。車いすなどでは対応できない状況を踏まえ、利用者の状況にあわせた備えが必要です。
まとめ
本記事では、介護施設における防災備蓄品と医療器具の重要性、そして具体的な準備内容についてご紹介しました。
昨今の自然災害の頻発や高齢化社会の進展により、介護施設は利用者の安全と安心を守るため、災害時にも迅速かつ的確な対応が求められています。基本の防災備蓄品として、食料・飲料水、衛生用品、災害対応用品を人数分十分に備えること、そして医療器具については常備薬や救急医療器具、AEDや吸引器など、利用者の個別の医療ニーズに合わせた適切な量の準備が必要です。また、BCP(事業継続計画)の義務化を踏まえ、定期的な点検やローテーション管理、地域の医療機関・行政との連携も欠かせません。災害時の命を守るため、各施設は最新のガイドラインに基づき、万全の備えを整えることが求められます。
関連記事
介護事業者必見!2024年のBCP義務化と対策ポイント
介護施設における職員の非常災害時の適切な対応とは?防災・非常時対応の手順とポイント


