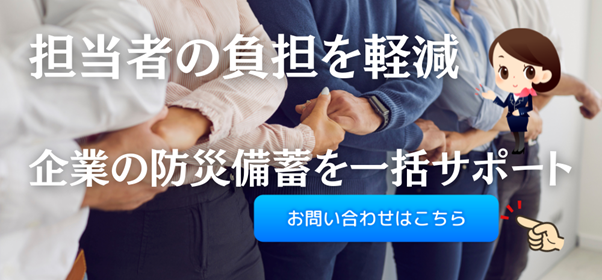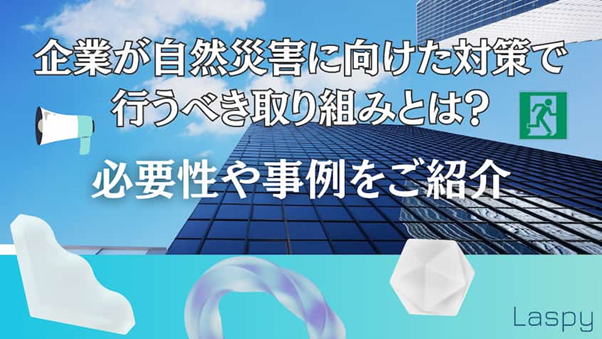日本は、地震や台風・豪雨をはじめ、様々な自然災害が発生する国であり、その頻度は年々高くなってきています。そのため、各企業では、これらの自然災害に向けて、対策や取り組みが重要視されており、防災活動に注力しています。
ここでは、企業が自然災害に向けた対策で、行うべき取り組みや必要性を解説すると共に、事例をご紹介していきます。

企業が取り組むべき災害対策とは?

自然災害による被害は、年々増加傾向にあり、発生頻度への危機感から、防災対策への意識が国全体として高まっています。特に、近年は、多くの地域で大きな災害が発生しており、その度に、マスメディアや各種SNSで、被害状況が広く知れ渡るようになったことが、防災への関心を高める一因となっています。
ここでは、災害大国とも言われている日本で、企業が取り組むべき対策について、詳しくご紹介していきます。
防災対策
企業の防災対策としては、災害が発生した際のリスク評価を事前に行い、来たるべき時のために、予め備える取り組みです。具体的な対策としては、地震や洪水などの自然災害に備えた建物の耐震化、避難経路の確保、避難訓練の実施、非常用の飲水や食料の備蓄、火災対策などが含まれます。
防災対策の目的は、災害が発生した際に、従業員や関係者の安全を確保し、物的被害を最小限に留めることなので、業務の継続や復旧対策については、重点を置いていません。
BCP対策
BCP対策は、防災対策とは異なり、災害が発生した際に、企業が事業の継続を確保するための計画です。BCP対策では、災害が発生した際、事業に影響を及ぼすリスク評価と、優先すべき「復旧業務の順位付け」と「再開手順(計画)」に加えて、代替施設の確保、データのバックアップ、人員を配置する手順なども含まれます。
BCP対策の具体的な内容としては、災害が発生した際にも、迅速に事業を再開し、顧客へのサービス提供を継続・早期復旧することを目的にしています。また、BCP対策は、防災対策とは異なり、物理的な災害対応だけでなく、情報技術の運用や管理など、幅広い側面による計画も含まれます。
そのため、防災対策は、災害が発生する前段階の対応であり、災害による被害の軽減や回避に焦点を置いています。一方で、BCP対策は、災害発生時において、事業の継続性を確保するために、業務の再開と顧客サービスの提供に重点を置いた対策です。

企業が災害対策を行うべき理由

ここまでは、企業が取り組むべき災害対策について、防災対策とBCP対策の観点から、ご紹介してきました。ここからは、企業が災害対策を行うべき「理由」について、わかりやすくご紹介していきます。
安全配慮義務
企業における安全配慮義務とは、従業員や関係者の安全を確保するために、企業が背負う「法的」・「倫理的」な責任のことを指します。一般的に、企業は、従業員や顧客、訪問者に対して、適切な安全対策を講じる責任を負っており、事業において様々な側面で適用されます。
例えば、法律には、労働者の健康と安全を確保するために「労働安全衛生法」を定めており、快適な職場環境の形成を行う必要があります。この中には、適切な防災訓練と安全装備の着用、危険物の適切な取り扱い、事故防止対策の実施などが含まれています。
帰宅困難者対策条例
東京都では、東日本大震災を機に「帰宅困難者対策条例」を施行し、自助・共助・公助の考え方に基づき「むやみに移動を開始しない」という、基本原則があります。また、埼玉県や千葉県などは、条例として施行されていないものの、近隣都市と連携して「帰宅困難者対策」に取り組んでいます。
帰宅困難者対策は、関東のみならず、各都道府県で取り組まれておりますが、東京都の場合は、地震発生時に3日間待機できるように、1人につき3日分9食の備蓄に努めることを、条例として求めています。
地球温暖化
日本では、地球温暖化による異常気象が頻発しており、水害や土砂災害をもたらす豪雨(1日200mm以上の大雨)を観測した日数は、統計的にも増加しています。これら、気象災害の背景には、深刻な問題である気候変動(地球温暖化)の影響があります。

企業におすすめする災害対策

ここまでは、企業が災害対策を行うべき「理由」について、わかりやすく解説してきました。ここからは、企業におすすめする「災害対策」について、詳しく丁寧にご紹介していきます。
備蓄品の管理
備蓄品の管理は、予期せぬ災害が発生した際、必要な物資を迅速かつ、安全に配給するために重要です。備蓄品の中には、食品の賞味期限や、消耗品の状況確認をはじめ、定期的な点検が必要なものもあり、補充や交換を行いながら、いつでも使える状態を保っていることが大切です。
さらに、備蓄品は、災害が発生した際、避難経路や避難場所の近くなど、迅速に取り出せる場所に保管しておくことも重要です。
防災マニュアルの作成
防災マニュアルの作成は、災害発生時に従業員や関係者が、混乱することなく、迅速かつ適切な対応を行うために必要です。防災マニュアルは、災害リスクへの評価や、事業継続計画(BCP)に基づき作成することで、事業の継続及び、早期復旧に努めることができます。
また、日本では、地震・台風・豪雨など、様々な災害が発生するため、状況に応じたマニュアル作成が重要です。
防災訓練
企業における防災訓練は、災害が発生した際、従業員や関係者の安全を確保するために行っています。人的な被害を最小限に抑えるためには、防災訓練を定期的に実施することで、災害に対する意識向上と、迅速かつ適切な行動が取れるようになります。

災害対策に向けた企業の取り組み事例
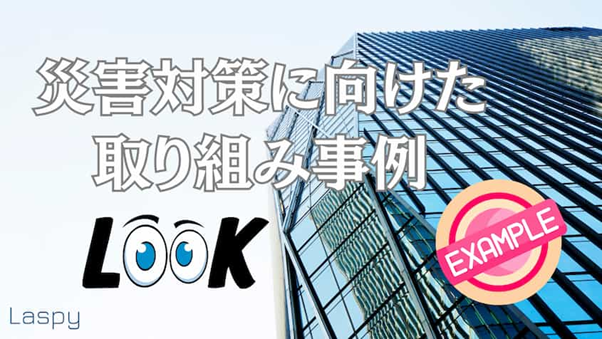
ここまでは、企業におすすめする「災害対策」について、わかりやすく丁寧に解説してきました。ここからは、災害対策に向けた「企業の取り組み事例」について、詳しくご紹介していきます。
第一生命グループ

画像出典:第一生命ホールディングス
第一生命グループは、グループで保有から運用と管理まで行っている5つの物件に対して、防災備蓄サービスの「あんしんストック」を導入しています。導入の目的は、地域全体の防災力向上であり、SDGs(持続可能な開発目標)目標11「住み続けるまちづくり」の実現を目指しています。
セブン&アイホールディングス

画像出典:セブン&アイ・ホールディングス
セブン&アイホールディングスは、人命最優先でありながらも、地域社会のライフラインとして役割を果たすべく、営業の継続と早期再開を目指しています。また、BCP(事業継続計画)の観点では、商品配送車両に使う燃料の確保を重要視しており、国内小売業としては初の「備蓄基地」を、北葛飾郡に設置しています。
北葛飾郡の基地には、燃料400klを常時備蓄しており、災害発生時には最大10日間、緊急物資や商品の配達に利用することが可能です。
ベルク
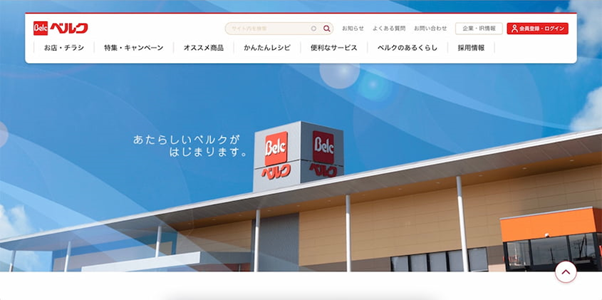
画像出典:ベルク
ベルクは、丸和運輸機関と「災害時の相互支援協定」を締結しており、通常の取引に加えて、有事の際に双方の事業継続を実現すべく、強固な協力体制を構築しています。災害発生時には、双方のリソースを活用しながら、業務を円滑に履行できるよう、相互支援体制を整備しています。

企業が提供している災害対策支援サービス

ここまでは、災害対策に向けた「企業の取り組み事例」について、詳しく解説してきました。ここからは、企業が提供している「災害対策支援サービス」について、ご紹介していきます。
Laspy
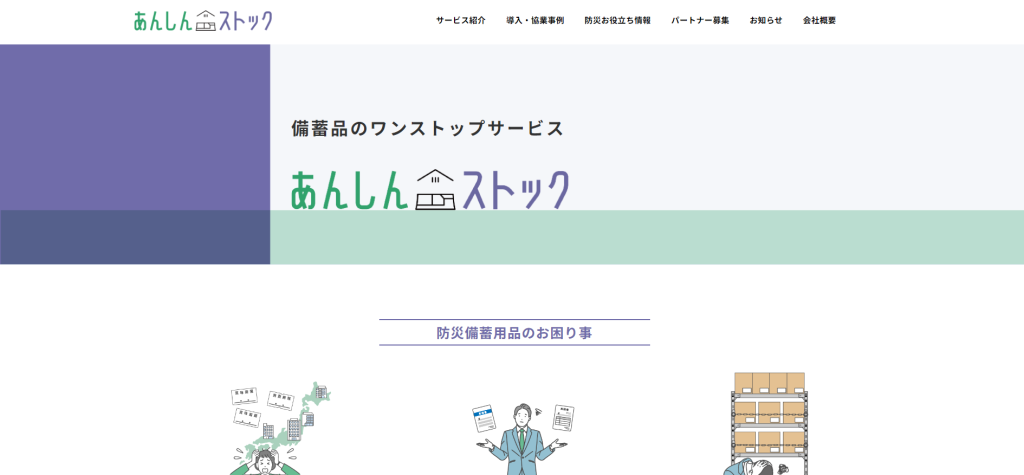
画像出典:株式会社Laspy
Laspyでは、企業に向けた災害対策支援サービスとして、備蓄品の保管・管理・提供までを一括でサポートしている「あんしんストック」を提供しています。あんしんストックでは、自社内に備蓄品を蓄えるスペースがない場合でも、安心して対策ができるように、災害発生時に「速やかな出し入れができる備蓄庫」の貸し出しも行っています。
サントリー
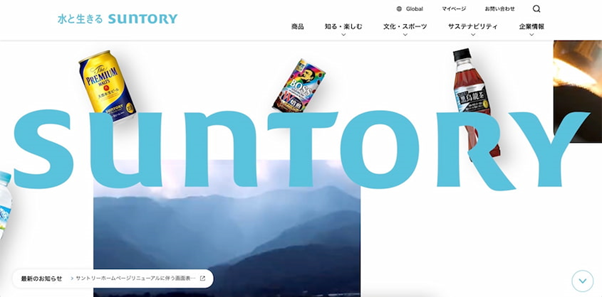
画像出典:サントリーホールディングス
サントリーでは、災害などの緊急事態が発生した際に、誰でも簡単に飲料水を取り出せる自動販売機を提供しています。例えば、災害発生時に対応可能な自動販売機は、無電状態時にワイヤーを引いて開扉できたり、ボタン一つで搬出できるので、無料で飲料水を配給することが可能です。
セコム

画像出典:セコム
セコムでは、地震などの災害時や、特別警報が発令された際に、企業の担当者に代わって、各従業員に向けて「安否確認通知」を送信しています。安否確認通知は、安否確認サービスの中に含まれており、GPS機能を利用したオプションとして、返信者の現在位置と報告内容・各場所の被災状況を地図上で確認できます。

まとめ
本記事では、企業が自然災害に向けた対策として、行うべき取り組みや事例について、ご紹介してきました。Laspyでは、防災担当者の負担を軽減すべく、備蓄品の管理から提供までを、一括でサポートしています。
また、Laspyでは、備蓄品の保管が自社内のスペースで確保できない場合には、近郊に備蓄スペースを用意することも可能です。ぜひ一度、Laspyの「あんしんストック」で、コストを抑えた備蓄対策をご検討されてみては、いかがでしょうか?